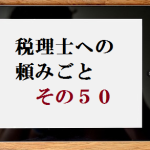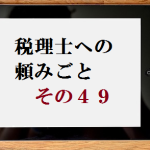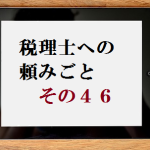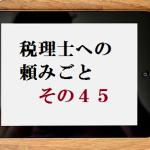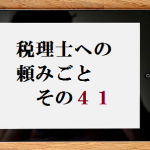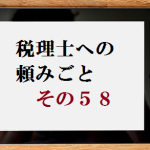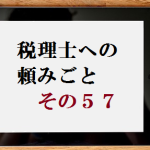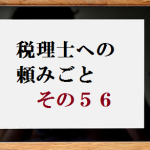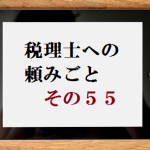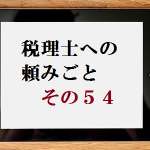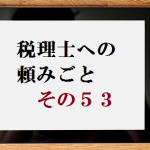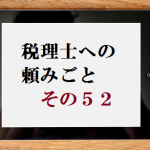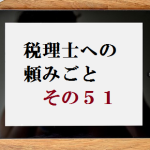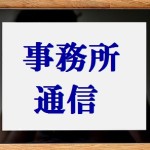2018/04/15

経営者の方と決算書や月次試算表を見ながら会社の状況を話していると、経営者の方が???と納得されないことがあります。経営者の経営感覚と決算書にズレがあるのです。
こんなときは決算書が会社の状況を上手く反映していない、「決算書が歪んでいる」場合があります。これを放置すると経営者は会社の状況を誤解して見誤ることになります。この歪みの原因と解決法について書いてみます。
決算書の歪みについては、こちらにも書いています。
・決算書の歪みを直す。建物の耐用年数を実態に合わせて短くしてもらう。
・決算書の歪みを直す。経営者の感覚で、もう回収できない売掛金は貸倒損失の処理をしてもらう
決算書の歪みとは
決算書は、会社の資産・負債を表示する貸借対照表と会社の1年間の売上・経費・もうけを表示する損益計算書で出来上がっています。会社の現在の実態をそのまま数字に反映して、経営の成績を判断するためのものです。
この決算書が実態と違う(あるべき資産や負債が載っていない・載っていても金額が多すぎる少なすぎる・経費が多すぎる少なすぎる・もうけが多すぎる少なすぎる)ことを決算書の歪みと言います。
歪みが生じる原因としては、経営者自らが粉飾決算を行っているような意図的なものを別として、経営者は気付いていないものがあります。よくあるものとして、『実際には会社に存在する財産・資産が決算書には表示されずに簿外資産になっていること』があります。
簿外資産・含み資産の例
実際には会社に存在する財産・資産なのに、決算書に表示されなかったり・表示されても少額になりうる例としては、こんなものがあります。
・生命保険の掛金の内、保険解約時に戻ってくる積立部分の金額
・経営セーフティ共済の解約時に戻ってくる積立部分の金額
・土地などの不動産の購入金額と現在の時価との差額部分の金額
・少額減価償却資産(30万円以下)として一括償却した資産の金額 等
例えば、会社の決算書上の資産として「保険積立金500万円」と表示されていても、実際その保険を解約すると1000万円の解約金がおりるケースがあります。このような場合、経営者としては決算書で会社の財産を把握しようとすると500万円であると誤解し、”1000万円-500万円=500万円”少なく認識してしまうことになります。
会社の資金繰りを検討するようなシビアなときに、この誤解の種を放置していると会社の将来を大きく読み違うことに繋がりかねません。そこで、簿外資産・含み資産が決算書に見えるようにすべきなのです。
簿外資産をリスト化する作業を手伝ってもらう
簿外資産・含み資産を見えるようにする方法としては、2段階あります。
第1段階・・会計処理の方法を変えて決算書に直接表示する
第2段階・・決算書に直接表示できないものは、決算書の添付資料に記載する
第1段階の具体例としては、経営セーフティ共済の積立金額があります。これは、会計処理の方法を変えることで決算書に表示することができます。当事務所では全て決算書に表示する方法で処理していますが、そうではない事務所も存在します。変更してもらえば、直ぐに直接表示になります。
第2段階の具体例としては、生命保険の解約金や土地等の不動産の時価があります。これらは決算書に直接表示することは難しいです。そこで、添付資料である内訳書に各々記載してもらいましょう。そうすれば、決算書と内訳書を見れば、会社の財産を見誤ることを防止することが可能になります。
この作業には、会社経営者の誤解を防止する効果だけではなく、決算書を見た銀行担当者などにも会社の財産を正確に知ってもらい信用性を高めるという重要な効果もあります。
ぜひ、税理士に手伝ってもらい決算書の歪みを直しましょう。